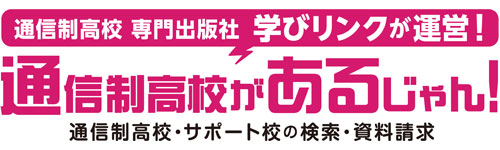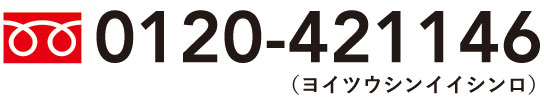新着情報
2025年08月25日
中学校と高等専修学校がともに「進路」について研究(東京都・千代田区)
8月5日(火)、アルカディア市ヶ谷 私学会館(東京都・千代田区)にて「令和7年度 高等専修学校進学研究会(第39回 中専協夏季研究協議会)」が実施されました。

中専協とは「東京都中学校高等専修学校進路指導協議会」の略称。東京都内の中学校教員、高等専修学校の教員がともに協力して中学生の進路について取り組む組織で、毎年8月に夏季研究協議会を実施しています。
39回目を迎える今夏は、東京学芸大学 伊藤秀樹准教授による講演のほか、東京都内の区立中学校によるキャリア教育の取組みに関する講演が行われました。
開会挨拶を行った本協議会の佐藤圭一会長は、働き方や学びが多様化し、教員に求められる知識量も増えていることを挙げ、「本研修会でより知識を広げてほしい」と参加者に呼びかけました。

続いて福田潤副会長も挨拶を行い、「今の時代の進路選択における職業訓練の重要性は増している。生徒のなりたい職業によっては、高等専修学校という選択肢があると念頭において指導してほしい」と述べました。

また、この日は来賓として、文部科学省より総合教育政策局・生涯学習推進課・専修学校教育振興室の米原泰裕室長も列席。米原室長は学校制度について触れながら、柔軟性が高く、子どもたちの特性に合わせた教育ができる高等専修学校の魅力を伝えました。

その後、前半に行われた講演では、東京学芸大学の伊藤秀樹准教授が『各校事例から見える高等専修学校の魅力とは』と題し、高等専修学校の制度や概要、4つの特色について解説。調理師や美容師などさまざまな「仕事に活かせる資格を取得できる」ほか、エンターテインメント系やクリエイター系での就職を目指す授業内容を展開し、「夢の実現をサポートする」学校が多くあることが説明されました。

また、高等専修学校の生徒のうち、不登校経験があるのは2割強。そのうち8割の生徒が入学後に改善傾向に向かっているというデータを示し、高等専修学校が「不登校経験者の自立を支える」という役割を担っている点に言及。
一方、合理的配慮が必要となる生徒は約3割、配慮が必要な生徒が4分の1以上在籍している学校は約2割。「多様な個性のある生徒の自立を支える」側面もあることから、障害の有無にかかわらず同じ教室でともに学ぶインクルーシブ教育を取り入れている学校の事例を紹介しました。
講演途中には、都内高等専修学校3校の教員が登壇し、各校の具体的な実践事例が紹介されました。
調理師科と美容師科の2つの学科をもつ大竹高等専修学校(東京都八王子市)は、生徒が取得できる資格や、実践授業が多く取り入れられたカリキュラムについて説明。
日本芸術高等学園(東京都国分寺市)は、俳優や声優、ダンサーなどを輩出しているエンターテインメント分野に特化した学校として、動画による紹介では、卒業公演でのクオリティの高いパフォーマンスを見せました。
芸術工芸高等専修学校(東京都多摩市)には、不登校経験のある生徒や合理的配慮を必要とする生徒が多く在籍。部活動や宿泊行事などの学校生活の充実や、提携する近隣の大学生ボランティア(メンタルフレンド)との交流など、「社会で自立して生き抜いていける力を育む」ための教育を紹介しました。
会の後半では、大田区立東蒲中学校によるキャリア教育の取組みについて講演が行われました。
登壇した谷山優司副校長は、東蒲中学校を取り巻く環境について、「交通の便が良く進路選択の幅を広くできる」「地域活動が活発で生徒も積極的にボランティアに参加している」という教育における立地条件の高さを紹介。
一方で、将来の夢や目標を持っていない生徒や、学んだことを実生活に結び付ける能力に課題をもつ生徒がいる現状も伝えました。また、外国語を母語とする家庭が増加し、日本語でのコミュニケーションが難しい場面も出てきているとのこと。
そのような背景を踏まえ、国際教育の強化のために実施している施策が紹介されました。
たとえば、教育施設「東京グローバルゲートウェイ」で行った外国人とのコミュニケーション体験では、英語を母語とする生徒がナビゲーターとして活躍。それまで言語の壁によりクラスでのコミュニケーションが課題となっていたものの、学習を通して周囲と打ち解ける効果があったと説明されました。
「イングリッシュデー」と呼ばれるイベントでは、様々な国籍の講師が屋台を出したり、生徒が自分の町自慢を英語で発表したりと、学校全体で盛り上がっている様子が紹介されました。
また、学校を準会場として英語検定を実施したり、外国語を母語とする生徒の補習や学び合いを目的とした「放課後日本語学習教室」を開設したりと、学習面のサポートも行われているそうです。
今後については、英語以外の言語にも対応できるような人材の確保や、保育園・幼稚園や小学校との連携も見据えて取り組みを続けていくという展望が語られました。
この日、会場には多くの都内中学校教員が集い、高等専修学校のしくみや特色について再認識したほか、中学校現場の課題も共有しながら、中学生たちの卒業後の進路について、中学校、高等専修学校が互いに見識を深めていました。