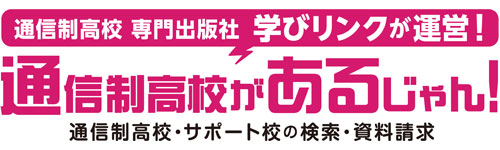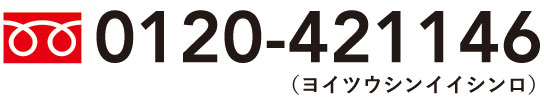新着情報
2025年11月11日
サポート校「通学定期対象外」1万5千人に影響か 全日制との補助金格差も浮き彫りに(全国私立通信制高等学校協会・実態調査)

全国の私立通信制高校でつくる全国私立通信制高等学校協会(私通協)が10日(月)、名古屋市内で「学校運営研究会」を開催した。今年度実施した実態調査の結果を報告したほか、文部科学省や専門家を招いての講演を行った。通信制高校の教育の質向上が求められる昨今、協会は各校との課題の共通理解や、調査による教育環境の実態把握、教育活動の社会的役割の周知を図る。
今年で3回目となる実態調査は、非会員校を含めて61校が回答。対象生徒数は9万2197人で、私立通信制高校全体の約38%を占めた。
報告では、在籍生徒が15歳から18歳までで全体の96.7%を占め、このうち中学校時代不登校であった生徒が59.5%、転入・編入生のうち前籍高校で不登校状態にあった生徒が47.8%と、いずれも入学者の約半数が不登校を経験していることがわかった。そうした中、在籍生徒の単位修得率は96.2%、3年間での卒業率は83.7%に上り、私立通信制高校が多様な背景を持つ生徒に手厚い支援を実現できていると示した。
一方、教育の質確保を図るうえで課題とされるのが全日制高校との補助金格差だ。学校運営に当てられる事業活動収入の状況を各校に聞いたところ、家庭から徴収する学生生徒納付金の割合は85.2%、国から私立学校に補助される経常費補助金は6.3%と、教育活動における生徒負担率の高さがうかがえる。これに対し、私立全日制高校は学生生徒納付金46.8%、経常費補助金37.7%で、補助金の割合が通信制高校と比較して高い。経常費補助金を生徒1人あたりに換算すると、協会調査校の3万1700円に対し、私立全日制高校は48万800円と大きな開きがある(※)。
※全日制高校の数値は日本私立中学高等学校連合会「令和6年度調査報告書」を基に算出
また、来年度から拡充が決まった国の就学支援金は、私立通信制高校が現行の上限29万7000円から33万7000円への4万円増額であるのに対し、私立全日制高校は上限39万6000円から45万7000円の6万1000円増額と格差が残る。こうした状況の中で、教育環境や質の向上といった運営基盤の安定をどのように図っていくかが課題だ。
通信制高校をめぐる課題としては、昨年12月にJR東日本が通信制高校と連携する学習等支援施設に対し、通学定期券や回数券の学生割引の発行を対象外とする通知を出した。これに対し、協会は25年1月にJR東日本側に要望書を提出。同年3月に、26年3月までの実施延長が発表されたものの、26年4月以降の対応については現在も協議が続いている。協会は今年10月にも再度、対象生徒への恒久的な発行を求める要望書を提出した。

(報告する吾妻俊治会長)
こうした状況を受け、協会は今年度の実態調査で新たに通学定期券の利用状況に関する項目を追加。その結果、通学定期券、回数券を利用する学習等支援施設の生徒が5775人いることがわかり、調査の回答率が私立通信制高校全体の3分の1を占めたことから、影響は1万5000人に上るとした。
活動報告をまとめた吾妻俊治会長は、今後意識すべき課題として、通信制高校が担う教育活動の「理解促進」「社会的信頼性の向上」のほか、「運営基盤の安定」の3点を挙げた。
いまだ不適切な学校運営を指摘される状況について「一生懸命に良い子どもたちを育てていることが理解されず残念でならない。各校が積極的に情報公開をして、社会に理解してもらうことが必要だ」とした。
一方、文部科学省は今後、通信制高校に対する点検調査を集中的に増やしていくとしている。吾妻会長は「むしろしっかりとした教育活動を見てもらい、社会的信頼を得ていくことも大切だ」。各研究機関との連携も視野に入れつつ「エビデンスに基づいた教育を推進していく必要がある」とした。

(議事進行を行った小椋龍郎事務局長(左)と吾妻俊治会長(右))
これを受け、第二部では、文部科学省担当者による講演が行われ、通信制高校における国の取組みや点検調査を踏まえての状況報告が行われた。報告後、出席した通信制高校関係者からは多くの質問が相次ぎ、通学定期券の問題や点検調査の調査方法、高等学校通信教育規程で求められる通信教育実施計画の在り方など、幅広い事案について、文部科学省の方針を問う意見が出た。
また、第3部では通信制高校の研究者で愛知学院大学准教授の内田康弘さんが、通信制高校の現状と今後の展開について教育社会学の観点から論じた。
内田さんは、増加する通信制高校の傾向について、これまでの教育政策との影響を分析。通信教育規程改正による教員定数の条件緩和がなされた2004年以降、新設された通信制高校の前身組織は「高校のみ」「各種・専修学校」「高校と各種・専修学校」とは異なる「その他」に区分される法人の新規参入が増えたと指摘。一方、教員定数の条件強化がなされた2023年以降では「各種・専修学校」「その他」の法人が減少し、多くが「高校のみ」とする法人で占めているとした。
また、各校の設置目的にも着目したところ、それまで高校中退や不登校への支援を主な設置目的としていた状況から、2020年以降は「不登校や高校中退者への支援とは異なる別の目的で学校が新設されている」と学校数増加をめぐるトレンドの変化を指摘した。
今後の将来像については「生徒の卒業後進路や適応、キャリアの見える化を図り、きちんと世間に対して教育効果を訴えていくことが必要」とし、教育の質確保を問われる側面において、多様な生徒に向き合う教員の質的条件の充実化の必要性も訴えた。

(研究講演を行った愛知学院大学・内田康弘准教授)
全国私立通信制高等学校協会は1971年に発足。急激に変化する通信制高校の状況を踏まえ、2022年に組織刷新と活動活性化を図り会則を改訂。通信制高校の社会的地位向上を目指し、現在は教育の質向上や各学校間の情報共有、行政への要望活動などを行っている。会員校は2025年11月現在で59校。「学校運営研究会」は今年で4回目の開催となり、会場には93名の関係者が集まったほか、オンラインでも110名が視聴。通信制高校の教員や経営者のほか、通信制高校を設置する所轄庁関係者、研究者も参加した。
(取材・文 学びリンク 小林建太)