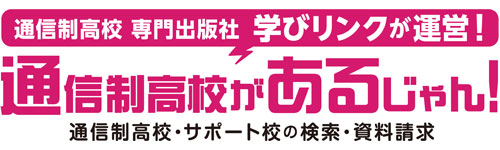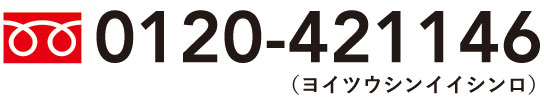新着情報
2025年10月21日
「新学会」創立20周年 下村博文元文科相など150名超が式典参加

多様な教育を実践する「新しい学校の会」(略称:新学会、理事長:大森伸一)が創立20年を迎え、周年を祝う記念式典が10月20日(月)、東京・千代田区内で行われた。
同会は2003年施行の構造改革特別区域法により開校した株式会社立の学校が集い、「学校設置会社連盟」の名称で2005年に発足。その後、一部会員校による学校法人への設置者変更などを受け2011年に団体名を現在の「新しい学校の会」へと改称した。以降は学校設置会社、学校法人、また学校設置を構想・計画する法人個人が集まり、次世代を担う人材育成、学校教育、学校経営の在り方を探求し実践する活動を続けている。教育シンポジウムを毎年開催するほか、2022年からは通信制高校の卒業生1万4千名以上を対象とした大規模な卒業生状況調査も実施。現在、正会員は17の通信制高校と専門職大学院。
下村元文科相「今後、通信制は高校生の3割に」
20日の式典では有識者を招いたパネルディスカッションが開かれ、元文部科学大臣の下村博文氏がパネリストとして登壇。通信制高校研究者の星槎大学特任教授の手島純氏、同会会員校で明蓬館高校理事長の日野公三氏らと意見を交わした。
近年の通信制高校の生徒数増の背景について、進行の大森伸一氏(新学会理事長)から問われた下村氏は「特に不登校の子どもたちが学ぶ受け皿としての役割は大きい。生徒数は今後さらに増加し、高校生全体の3割が通信制高校生となる日も来るのではないか」と考えを示した。
手島氏は通信制、定時制、全日制それぞれの現場を教員として経験した観点から「工業社会的な既存の教育から脱してSociety5.0に対応できる、あるべき教育を一番体現できるのが通信制ではないか」と魅力を語った。
一方、日野氏は「危なっかしい状態にあるのではないか」と懸念を示した。「ただ『学校に行かなくてよいから』という生徒も受け入れてはいないか。学びづらい、生きづらいと感じている生徒を迎えるのが通信制の本来の役割。どのような生徒の役に立ちたいのか、その生徒が社会参加する姿を思い描き、どのような社会にしたいかを改めて考える必要がある」と警鐘を鳴らした。

(下村博文氏・元文部科学大臣)

(手島純氏・星槎大学特任教授)

(日野公三氏・明蓬館高校理事長)
今後の通信制高校に求められることについても、それぞれの立場から意見が交わされた。
下村氏は「卒業後の進路についてもサポートすることが通信制高校に対する世間の評価に繋がっていく」と期待を寄せる。一方、行政が教育現場の声を受け止め政治を変えていく必要性にも触れ、今後も行政に働きかけていくと意欲を示した。
手島氏は「通信制高校はアバンギャルド」だとし、「芸術に限らず常に前衛のものが新しい道を切り拓いていった。現状の通信制業界は良い面も危なっかしい面もあるが、良い面を伸ばし、襟を正して質をしっかり確保していかなければならない」と述べた。加えて、通信制高校の教員の意欲の高さに触れ、学校として待遇改善や労働条件の見直しの必要性について提言した。
日野氏は「学校に行くか行かないかは手段であり、最上位概念は生徒が学習権を行使するということ。手段を目的化してはいけない」と話し、「AIによる技術革新が進む今、人間にしかない、自ら問いを立てる力や直観力、感性を磨いていく現場として通信制高校の教育は有効である」と述べた。
150名超が情報交流

パネルディスカッション後には会場を変えて懇親会が行われた。
挨拶をした大森伸一理事長は、会員校の通信制高校在籍生徒数が4万人を超えたことに触れたほか、「卒業生調査で蓄積された貴重なデータは生徒指導に大いに生かされている。今後もシンポジウムの開催、アンケート調査、卒業生の進路を向上させるための支援に注力するとともに、一緒に生徒支援に協力いただける賛助校の拡大を図っていきたい」と述べた。
また、「生徒指導において3つの重要なワード」として「ほめる、励ます、視野を広げる」を掲げ、「新しい学校の会は、未来を担う若者の成長に尽力したい」と述べ、関係者に対し、これまでの支援に感謝の意を伝えた。

(大森伸一氏・新しい学校の会理事長)
そのほか来賓として下村博文氏が挨拶をしたほか、新たに賛助会員となった新潟青陵高校、神奈川ビューティー&ビジネス専門学校、開志創造大学の代表者が登壇。また、歴代の理事長を務めた反町勝夫氏、日野公三氏、桃井隆良氏らがそれぞれ挨拶をしたほか、同志団体として全国私立通信制高等学校協会会長の吾妻俊治氏が挨拶を述べた。
会の終盤には、事務局より2分間インタビューが行われ、一ツ葉高校教頭の長澤利弘氏、八洲学園高校校長の林周剛氏、中央大学特任助教の澁川幸加氏、株式会社ライセンスアカデミー教育事業部長の尾高忠明氏が、それぞれ立場から式典の感想や今後の期待などを寄せた。
約2時間行われた懇親会には総勢150名を超える関係者が参加。多種多様な参加者がそれぞれの立場から意見を交わし情報交流を図った。
文科省を招いての意見交換会

なお、この日、記念式典を前に、同会は文部科学省を招いての教育意見交換会を実施している。講師として登壇した文部科学省初等中等教育局参事官の橋田裕氏は、通信制高校に対する国の方針や教育の質確保に向けた調査研究の状況について報告。また、現在議論が進められている高校無償化、JR東日本によるサポート校の通学定期券の取り扱いに関する動向についても触れた。
出席した関係者からは、サテライト施設の位置づけや無償化に関する通信制高校の対象範囲、通信制高校の運用における都道府県ごとの違いなど様々な視点から質問が投げかけられた。
通信制高校に対する今後の国の方向性について、橋田氏は「数万人規模の学校が出てくる中で、教員配置や施設整備の在り方を含めた質の確保を考えざるを得ないところがある。中規模、小規模であってもきめ細かく丁寧に運営している学校もあるが、我々としては生徒目線に立った質確保を第一に考えていかないといけない」と説明した。
(取材・文:学びリンク 小林・小野・片山・柳・中曽根)
●新しい学校の会(新学会)
●学びリンク合同相談会