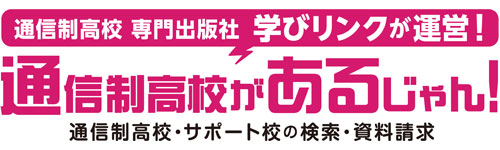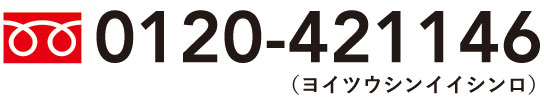椎名雄一先生コラム『不登校に効く心理学の話』49
どの「前提」で関わるかが大事
2024年9月18日
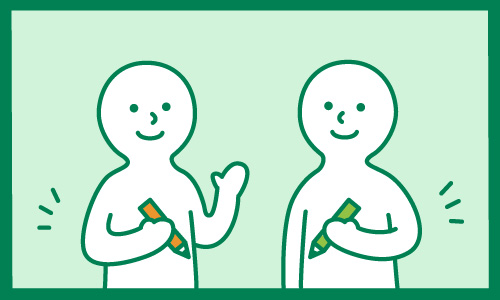 |
日々皆さんとメッセージのやりとりをさせていただいたり、カウンセリングをする中で気づいたことや傾向などをこのコーナーでお伝えしています。
人の人生に口を出すときにはひとつだけ注意したいことがあります。
それは「前提」です。
「不登校が悪い」という前提で関わるのと
「不登校も選択肢のひとつ」という前提で関わるのはまったく意味が違います。
「今回は社会と折り合いがつかなかった」という前提で関わるのと
「子どもが間違っている」という前提で関わるのも違いますね。
少し切り口を変えると
「私は子育てを十分にやってきた」という前提と
「私の子育ては間違っていたかもしれない」という前提でも大きく違います。
ジェネレーションギャップの観点では
「正解はひとつでそれを学んで合わせなくてはいけない」という前提と
「答えは多様で人によって違っても良い」という前提では違いますね。
不登校の最中にいる中高生の人生に介入するような会話をするときに上記の前提の2択が不一致だったとしたらメッセージは届かないかもしれません。
「不登校が悪い」という前提では学校に戻すことが大事と考えますし、「不登校は選択肢のひとつ」という前提ならばさまざまな生き方を探したり、人生を輝かせる方法を発見しようとしますよね。
お子さんが「人生」を考えているときにもし保護者が「学校に行く」という限定的な発想で関わっていたとしたら会話が成り立つはずがありません。
多様性の社会は「前提」がたくさんある社会ですから自分自身が想定していない基準で生きている人がたくさんいることを頭に入れておくことは育児に関わらず重要になっていきそうですね。
例えば「保護者」という言葉がありますが、なぜ「お父さん」「お母さん」のような呼び方をせずに「保護者」というかというとそれでは当てはまらない家庭があるからです。祖父母や里親、未成年後見人なども「保護者」にあたりますし、一時的に子どもの世話をする親族も「保護者」です。
「保護者」=「お父さん」「お母さん」
という前提のご家庭もあれば
「保護者」=「おじいちゃん」
という前提のご家庭もあるということですね。
それ以外にも「右利き前提」で作られているものも多いですね。
「自動改札」「はさみ」「クリアファイル」などは「右利き」であることが前提で作られています。(最近では考慮されたものも増えてきました)
気をつけたいのは「右利き」の人にとっては
「自動改札」や「はさみ」に違和感を感じない点です。
「学校に行けるのが当たり前」の人が「右利き」だとしたら
「学校に行けない状態」の人は「左利き」のようなものです。
その人が日々のやりにくさ、生きにくさを感じていることすら気づけないかもしれません。
それだけに慎重に相手との「前提」の違いに気をつけたいですね。