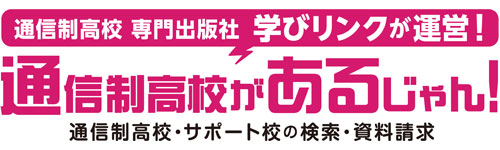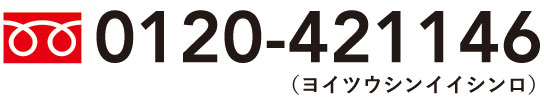椎名雄一先生コラム『不登校に効く心理学の話』56
「進路」の話をバラバラにしてみる
2025年2月3日
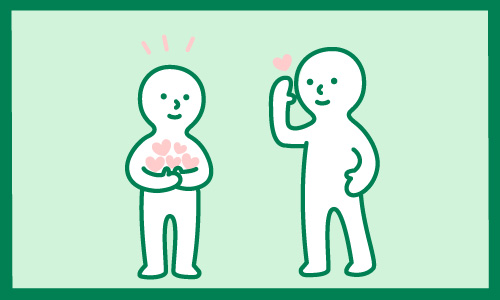 |
日々皆さんとメッセージのやりとりをさせていただいたり、カウンセリングをする中で気づいたことなどをこのコーナーでお伝えしています。
進路や将来のことをお子さんに聞くと「答えてくれない」「機嫌が悪くなる」「反応が薄い」と感じる保護者の方は多いと思います。タイムリミットがある進路の話がなかなか決まらないと焦ってしまいますし、途方に暮れてしまうこともあると思います。
そんな時には「進路」というあいまいすぎる大きな概念を少しバラバラにすることをお勧めします。私たちも「世界平和」といわれるとピンときませんが「分別のゴミ箱」とか「募金」といわれると少しイメージしやすくなります。「進路」というのは具体的に言うと「好き嫌い」の延長にあるものです。
人生を決めることは自分の「好き」を多めにして「嫌い」を少なめにする作業とも言えます。デザインが好きだなと思えばそういう要素が多めの「進路」が良さそうですし、大勢の人と関わるのが嫌いならば少人数でできる「進路」が向いています。もちろんそれだけの要素ではなく、資格が取れるかとか機会があるかなどの要素ももちろんありますが、ゼロベースでまず「進路」を考える時に大事なのは好き嫌いです。
ゲームの中でも好き嫌いがあります。
好きな戦い方。好きなキャラクター。好きな武器。嫌いな行為。それらはゲームの中に限ったことではありません。ゲームで「集める」のが好きな子はリアルでも機会があれば「集める」ことを楽しめたりします。「集める」が仕事になれば能力を発揮できるのかも知れません。しかし、好きなことを仕事にしたくないという好き嫌い、、嫌いがあることもあります。それらはその子の価値観です。
その価値観をできるだけ多く把握して、どうしても譲れないものを中心に考えていくと自然と「進路」が見えてきます。
「医師」「会計士」「山岳ガイド」「ヘルパー」「家事代行」のように社会にはさまざまな職業がありますが、「誰かを支える」という意味ではこれらは似ています。
お子さんの中で「自分は支えるのが好き」「自分は集めるのが向いている」そんな会話ができた上で周囲にいる大人が実際の職業と結びつけ、関わる機会を作ったら「進路」は見えてきます。もし、周囲の大人が目の前の子どもに関心がなく、社会のことをよく知らないのであれば、無責任に「進路は?」と聞く前に子どものことをよく知ることと社会をよく知ることをやっておきたいですね。
いきなり「進路」と聞くよりも好きなことを10個。嫌いなことを10個丁寧に聞いてあげた方が結果として進路の話につながりやすいかもしれません。