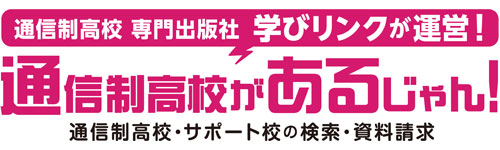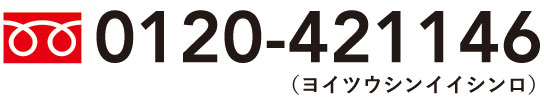椎名雄一先生コラム『不登校に効く心理学の話』57
答えがあることとないこと(2種類の学び)
2025年2月17日
 |
日々皆さんとメッセージのやりとりをさせていただいたり、カウンセリングをする中で気づいたことなどをこのコーナーでお伝えしています。
お子さんが中高生の時期、親としてどんな学びを提供したら良いかについて悩むことが増えてくるのではないでしょうか。この時期は特に「勉強しなさい」「進路はどうするの?」といった言葉が飛び交いがちですが、その背景にある「答えがある学び」と「答えがない学び」の違いを意識することがとても重要です。
今回は、この二つの学びの違いについて考えてみたいと思います。
「答えがある学び」というのは、数学の計算問題や歴史の出来事、英単語の綴りなど、明確な答えが存在する学びを指します。こうした「答えがある学び」は論理的思考を鍛え、事実を正確に理解するための土台を築く重要なプロセスです。たとえば、数学の問題を解くことは、決まった手順を用いて論理的に物事を進める訓練となり、歴史の事実を学ぶことは、過去から学び、未来の選択をするための知識を蓄えることになります。
これらの学びは、学校のカリキュラムに沿って「正解」を求められるものであり、いわば「狭義の勉強」とも言えるかもしれません。
一方で、「答えがない学び」というのも私たちが生きる上で非常に重要な学びです。たとえば、進路選択や将来のキャリア、人間関係、芸術の表現など、こうしたテーマには「正解」がありません。それぞれの人が自分なりに考え、試行錯誤しながら答えを見つけていくものであり、「正解」が一つに定まらないからこそ、深く悩むこともあれば、大きな成長のきっかけになることもあります。
たとえば、「進路」について考えることは、どの学校に行けば正解なのかを問うよりも、「自分はどんなことが好きなのか?」「どんな未来を描きたいのか?」といった自分自身の価値観を見つける作業です。ここに明確な答えはなく、一人ひとり異なる道を模索することになります。この「答えがない学び」に向き合う力を育むことは、子どもたちが将来、自分で人生の舵を切るために非常に重要な力となります。
学校では「答えがある学び」が多いため、子どもたちは「正しい答えを出す」ことが求められる環境で育ちます。そのため、時として「答えがない学び」に向き合う場面で戸惑いや不安を感じることがあるかもしれません。たとえば、「進路どうする?」と親から聞かれたとき、まるで「正しい答え」を期待されているように感じ、圧迫感を覚えるお子さんも少なくありません。
また、「不登校」のような問題も「答えがない課題」の一つです。「何が正解か分からない」という状況の中で、親や子どもはそれぞれ試行錯誤を重ねながら、自分たちにとっての最適解を見つける努力を続けていく必要があります。大切なのは、答えが見つからないことに不安を感じるのではなく、むしろその状況を受け入れ、前向きに考え続けることです。
「答えがある学び」はもちろん大切ですが、それと同時に「答えがない学び」に向き合う力を育むこともとても重要です。子どもたちが大人になって社会に出ると、正解があらかじめ用意されている場面は少なくなります。「どう生きていくか」「どんな人生を送りたいか」といった問いに向き合うために、日々の生活の中で「正解がない問い」に取り組む経験を積むことが、最終的にはお子さんの成長につながります。
正解がないことを恐れず、その不確実性の中で何を見つけ、どう成長するか。それを支えるのが、私たち親の役割です。どうかお子さんがその旅路で自分なりの道を見つけていけるよう、温かく見守り、サポートしていきたいですね。